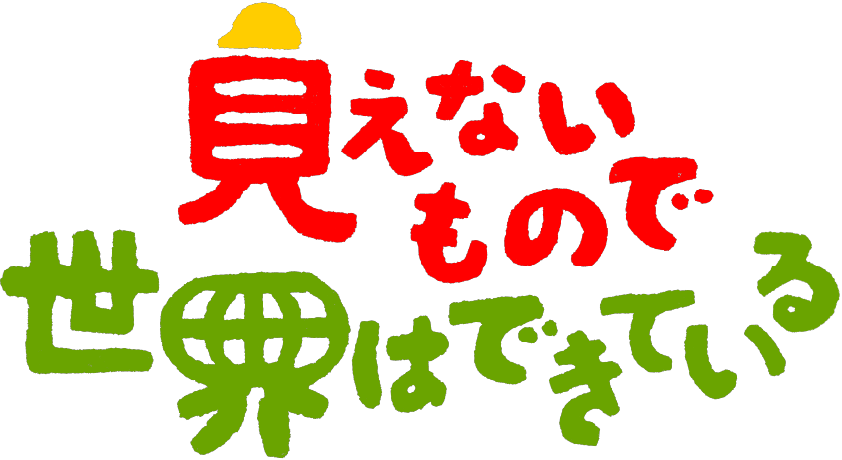文/神吉 弘邦 写真/桑嶋 維(怪物製作所)
ー
文化庁長官を務めた近藤さん自身、文化というものに関心を持たれたのは、いつごろのことでしたか?
近藤先生
普通の子どもといたって変わらない生活を送っていたと思いますが、小学校2年生くらいのときに家への帰り道で、ある大きな洋館から聴こえてくるピアノのメロディがきっかけでした。おそらく少し年上の子が弾いていたショパンの幻想即興曲だったと思うのですが、自分でも弾いてみたいと憧れたのです。
だから最初は西洋文化にベッタリでしたけれど(笑)、次第に海外へ行くようになると自国の文化について説明しなくてはいけない機会が増えて、日本文化に目が向くようになったという経緯です。


近藤さんは外交官時代のお仕事で、文化について語る機会が多かったんですか?



近藤先生
はい。お互いの文化への理解は、とても重要ですからね。外交は大まかに言うと、2国間の外交と、OECD(経済協力開発機構)など国際機関の加盟国間で行われる多国間の外交があります。そうした会議を仕切っているのは、やはり欧米の国々です。インドなど他の地域から来た方々も、西洋合理主義的発想を身につけて弁論が巧みな人が多いです。
ー
―言葉がとても大切なのですね。
近藤先生
自分の言いたいことを120%にまで膨らませて自己主張するというのは日本の文化になじみませんから、つい発言が減ってしまいます(笑)。
しかし2国間の外交で成否が決まるのは、お互いに信頼を育めるかどうかなんです。そのためにも「この人の家族構成はこうで、こんな音楽が好きで、自分と少し趣味が合うところがある」といった文化的なところがわかり合うようにする。相手の個人的な思想だったり、感性だったり、そうした面から尊敬の念が生まれますから。そこから、人間としてのやりとりが始まる。


近藤先生
多国間の交渉は、さらに難しくなります。オープンな会議場という空間で、みんな建前では国益を背負い、場合によってはメディアも入っているわけですから、下手に妥協なんかできないぞ、と張り合う。その裏では根回しや調整もするわけです。その際にも、互いに尊敬できるものを持っている人同士は、個人としての心情を共有して「このあたりが両者の落としどころ」といった交渉ができるのです。
まさに人間同士のやり取りだなぁ、という感じがします。



近藤先生
そういう場面で憧れを持たれるのが、やっぱり文化なのだと思いますよ。
ー
海外から見たとき、日本の文化に特徴的な面はありますか?
近藤先生
日本の文化で根強いのは「人は自然の一部であり、しかも常時それは流れている。固定された人間、自分というものが存在するわけではない。今という時間や存在は、流れの一瞬を捉えただけである」という発想です。
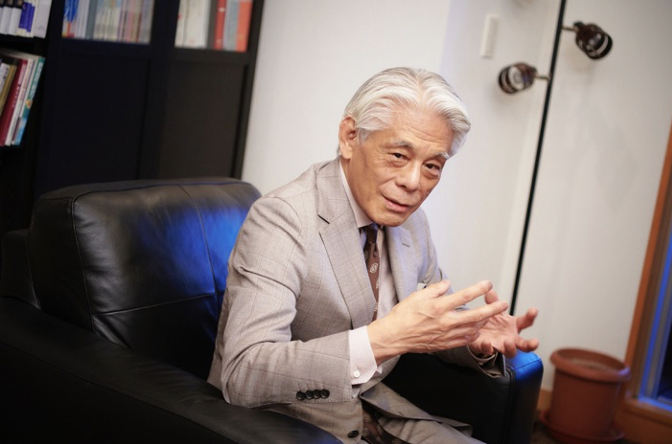
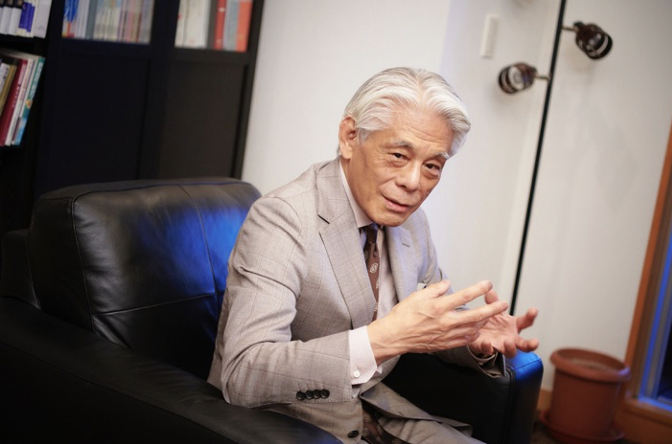
近藤先生
それが、有名な鴨長明の「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし(※)」という『方丈記』の書き出しでした。
(※現代語訳:川の流れは途絶えることなく、そこに流れている水はもとの水とは違うものだ。水面の泡は、消えたり生まれたりして、その状態ではいつまでも存在しない。それは、人や住まいについても同じである)
ー
今から800年以上も前に、日本の自然観をズバリ表現しているのですね。
近藤先生
その通りです。西洋合理主義的な感覚からすると、「ものごとには実体があり、その実体は不変である、永久に同じである」という大きな前提があるんですね。しかし、日本の文化ではそうではなく、「どんなものでも常に移ろっている。したがって大事なのは、その実体が何かではなく、それがどのように移ろっていくのか。その変化の流れを見定めることこそが、本質を見るうえでは大事なのだ」という考えがあります。
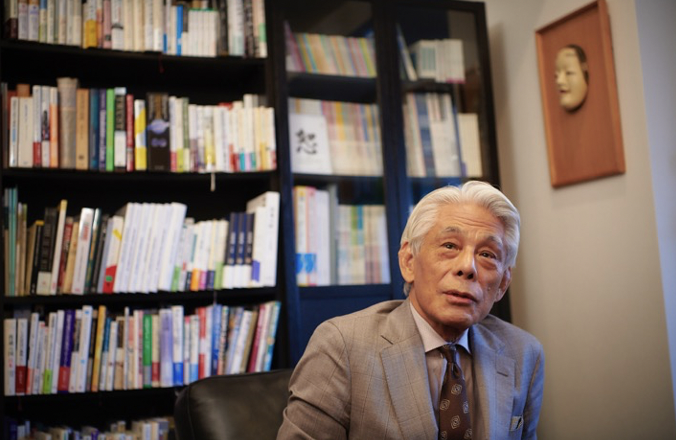
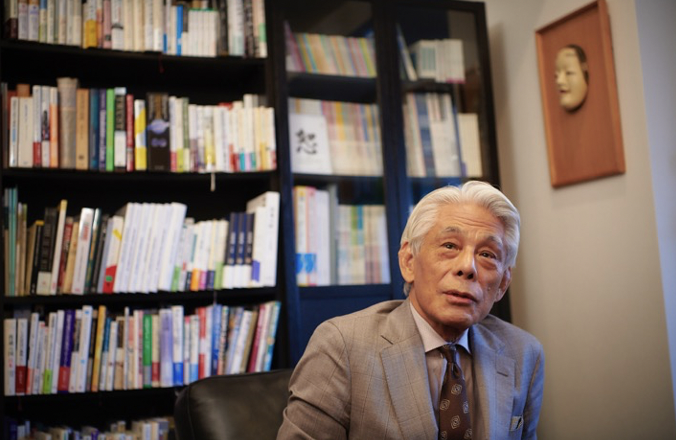
近藤先生
1日の時間には、昼と夜がありますよね。西洋合理主義的な考えだと「昼は昼、夜は夜」という二元論です。でも、日本の文化では昼と夜だけではなく、だんだん夕方に暗くなっていき、また明け方にほのぼの明けてくるように、ずっとものごとは動いている。満月や朧月もあれば、三日月もある。「移ろいの中に何らかの本質がある。自分だって自然の一部なんだから、命の繋がりの中で回っている」と捉えるのが日本の自然観です。
僕たち酵素も、そうやって移ろいの中で命を繋ぐ仕組みの一部なんですね……。



近藤先生
人はある一瞬の存在にすぎないし、1つ1つの個体の命は短くて、結局はエントロピーの力に負けて滅びてしまう。でも、子孫を残すなり、ウイルスのように変身したりして、酵素も含めた自然と支え合い、命を預け合って、ぐるぐる回って38億年続いてきました。ここまでは言語化していないと思うのですが、そんな気持ちが日本の文化では感覚的にあると思うのです。
だから、熊や鯨の命をいただくときには、すべてを余すところなく使い果たします。微生物を弔うための塚を建てるし、船だって壊れたら社に祭りますよね。使わせてもらったものに対して、ちゃんと感謝をする文化が身についています。最近ではあまりしないかもしれませんが、針供養でも「ご苦労さん」と言って柔らかい豆腐に刺してあげて、私たちは最期に感謝の気持ちを表してきました。
ー
ここまでのお話、酵素くんはどう聞いたのかな?
天野エンザイムの研究者さんたちは、それこそ電子顕微鏡のような技術で今まで見えなかったものが見えるようになったことで、研究の道に興味を持ったんだと言っていましたよ。だから、まだ見えていないものを他人に説明するというのは、なんて難しいことなんだろうと感じます。日本の文化を海外の人に説明するのって、きっと大変ですよね。



近藤先生
言葉だけで解説するのは、やっぱり難しいですね。だから実際に日本に来てもらって、四季を感じ、日本人の生活ぶりを見て、体験してもらうのが一番です。日本の文化や自然観、発想や考え方を伝えることは、これからますます大切になると思っています。環境破壊にも関係がある話ですし、野生動物の種の数が減っている問題に対しても意義がありそうです。
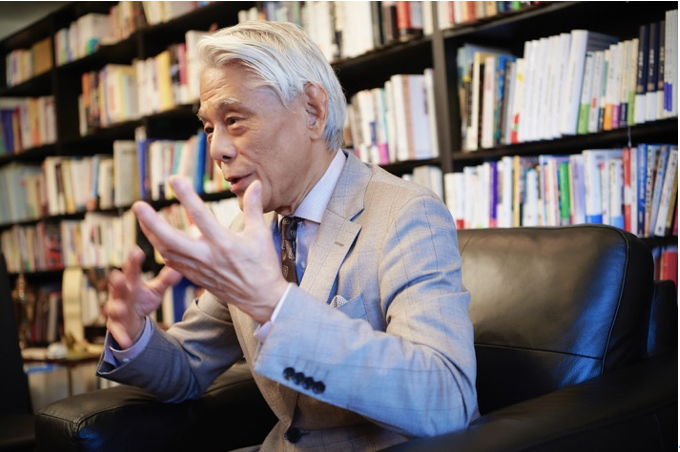
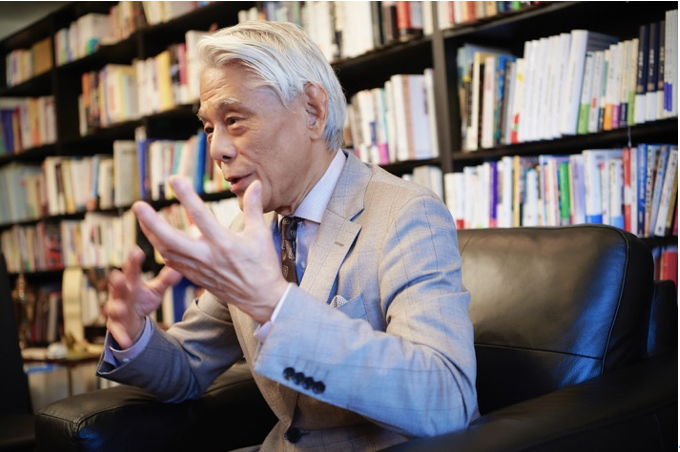
僕たち酵素に関する話でいうと、まだ微生物全体のほんのわずかしか人間は知らないと言われています。これから科学技術が発達すれば、これまで見つからなかったものが見つかるかもしれません。ただ、もしかしたら、それを待つ間にも数が減っているのかもしれません。



ー
最後に、文化と同様、この世界をつくる「目に見えないもの」である酵素の研究について、近藤さんが感じる期待をお聞かせください。
近藤先生
これから科学技術がさらに発展すれば、酵素についての客観的な知識も増えると思います。そのときに大切なのは、世界は目に見えないさまざまなものによってつくられ、動いているという意識です。
人間の目で見えるもの、耳で聞こえるもの、舌で味わえるもの、手で触れられるもの、それらはすべてのもののうち、ごくごく一部にしか過ぎません。人間は、自分や自然のことをすべて知っていると思っていたけれど、どんどん新しいことがわかってくるにつれて、全然そうではないのだとわかってくるはずです。


近藤先生
これまでの文明の発達によって人間が持ち始めていた傲慢さ、そういったものから離れて、自然に対する謙虚さや尊敬の念であったり、自然の摂理を重んじる姿勢を持つ大切さであったり、そういう気持ちが芽生えてくればいいですね。
そういう意味で、ますます酵素の研究が果たす役割は大事ですし、その研究をされる方たちは、いろいろなかたちで成果を社会に還元されていくのだと思います。


近藤さんのお話から、日本文化に根付く「自然の一部である」という謙虚な姿勢が、これからの科学にとって重要なヒントになると教えていただきました。
当社は酵素の研究開発を通じて、目に見えない微生物の力を活用しています。その過程で、私たちが制御できると思っていた現象も、実際には自然の摂理の中のごく一部に過ぎないことを日々実感しています。
酵素業界に限らず、西洋合理主義的なアプローチと日本的な自然観を組み合わせることで、より良い研究開発が可能になるはずです。私たちは目に見えないものへの敬意を忘れず、自然との調和を意識しながら、これからも酵素の無限の可能性を追求していきたいと思います。
この世界のあらゆる場面で活動する酵素、その新たな可能性を求めて。
現在、さまざまな分野で活躍中の人々のもとを「酵素くん」と一緒に訪ね、お話をうかがうコーナーです。