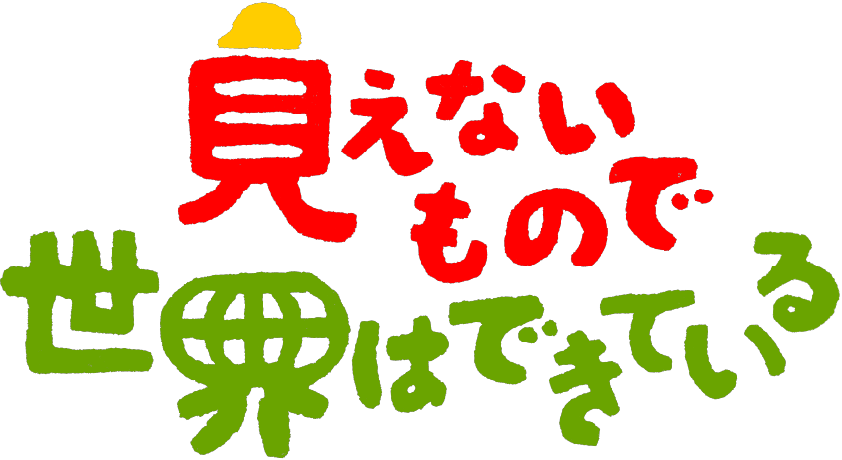ー
今日お邪魔しているのは、外務省出身で初の文化庁長官を務めた近藤誠一さんが主宰する「近藤文化・外交研究所」です。大学教授の研究室のような落ち着いた雰囲気を感じるのは、面白そうな本が並んだ本棚があるからですね。
あっ、僕は「ポケモン」について真面目に語った本を発見しました!



近藤先生
人間を知るには、いろんな角度から攻めたほうがいいんじゃないかなと。本のジャンルが多様なのは、ご献本をいただく機会も多いからですね。以前はきちんと分類していたのですが、今はわりとランダム。でも、偶然隣り合う本の内容が結びついて面白いでしょう?


ー
本以外にも、このお部屋には世界各地から集められた「面」などの工芸品、絵画や書などの美術作品が飾られていますね。
近藤先生
こちらの書は、書家の紫舟(ししゅう)さんの作品です。書が面白いのは、もともと意味がある字を、さらに人が思いを込めて書くからです。また、墨で書いた字の素敵さに加えて、残された「余白」も大きな意味を持っています。
彼女は、余白を体感させる面白い展示をしたことがあります。2次元から書が飛び出し、彫刻のように字をドンと立体化させたのです。そのときの周りの空気、全部が余白でした。


海外の人たちにそういう説明をすると、どんな反応が返ってくるんですか?



近藤先生
ヨーロッパにもカリグラフィーなどの文字を綺麗に書く芸術があります。彼らも書への関心は高いので「すごい」という声が上がるのですが、それは「字が立体になったからすごい」という素直な感想です。余白の意味を説明しても、すぐには伝わらないことが多いですね。余白というのは無駄なものであり、表現したものの余りととらえている。
しかし、日本では余白を重んじます。音楽でもそうだし、言葉と言葉の「間」の長さによってもニュアンスが違ってくる。ほとんど「見えない、聞こえないコミュニケーション」が大事で、そうした部分に精細さがあるのが日本の文化なのだと思います。
余白とか間とか、なにもないものを大切にしているんですね。



近藤先生
そうです。たまたま形や色になっていないだけで、やっぱり「なにか」なんですよ。英語ではボイドとかスペースと呼ばれる何もない空間はゼロだとされます。けれど、日本の文化では決してゼロではない。それは一つの存在なんです。
天野エンザイムの社長さんが、前に近藤さんから「科学系の知識はビジネスだったり、ものを開発したりするのに役立つけれど、人生の岐路に立ったような重大な場面では、歴史やリベラルアーツなど、科学とは異なる文化系の知識を学んでこそ、自分で未来が選択できる」というお話を聞いたとき「なるほど!」と思ったんだそうです。



ー
そこで、まずは「文化とはなんだろう?」というところから、お話を伺いたいです。
近藤先生
文化もある意味で、酵素と同じく「目に見えないもの」なんです。たとえば、地域の共同体や家族が一貫して持っている文化。それは人と人の心を繋ぐものです。心だって見えません。心は心臓じゃないし、脳のことでもないから、いくら要素還元的に分解しても、分子や原子で見つからない。私たちはお墓や慰霊碑に行くけれど、そこに心はないし、命もないわけです。将来はわかりませんが、まだ近代科学的な手法で人の心は分析できていません。
その「見えない心」を表現する手段として、ありとあらゆる芸術表現が生まれます。有名な芸術作品でも、素人が粘土でつくった茶碗でもいいのですが、それらの物質の奥には、すべて人間の心があるということです。


ワクワクとか、ドキドキとか、そんな心の動きだって他人の目からは見えませんよね!



近藤先生
その通り。人間社会というものは、愛であったり憎しみであったり、悲しみであったり希望であったり、目に見えないのものででき上がっているということです。
日本語の「見る」という表現を考えても、物理的な情報を目でとらえる意味だけではなく、競技相手の「戦略を見る」とか、恋人の「内心を見る」とか、視覚を使わない状況でも登場します。
言い換えると「推し測る」とか「想像する」という意味ですね。まるで、第六感みたいな感じですね。



近藤先生
視覚に加えて、聴覚、嗅覚、触覚、味覚。五感を受容する器官が私たちには備わっていて、それを使って世界を把握しています。でも、わかるのは世の中に存在するもののうち微々たるものだけです。目も可視光線が反射するものだけの情報をとらえるし、耳も全音域が聴こえるわけではありません。


近藤先生
科学が発達したことで、顕微鏡という道具で肉眼では見えないものが見えるようになったし、ITによって遠く離れた人とも話ができるようになりましたが、その力にもやはり限界があります。私たちは目に見えるもの、手で触れられるものがこの世界のすべてと思いがちですが、本当はまったくそうではないのです。
電子顕微鏡でも宇宙望遠鏡でも、科学の道具が発達すると、逆にこれまでは見えなかったものが、どんどんわかってきますよね。



近藤先生
目に見えるもの、聴こえるものを増やすという科学の意義は大きいですが、便利な道具がいくら発達しても、森羅万象を把握することは絶対にできない。それなのに「見えないものは存在しない」と考えるのは、とんでもない人間の傲慢さだと思うのです。
謙虚さを持って自然に接して行かないと、いずれは過ちを犯します。もう犯しつつあるような気もしますけれど、目に見えないものだからこそ素晴らしいものだという心がけを持つことが大事ではないでしょうか。
ー
近藤先生は、著書や講演で「人間の五感の限界を理解して、自然への謙虚さを備えるのが日本文化だ」とおっしゃっていますね。
近藤先生
西洋人、特にヨーロッパで近代合理主義の文明を担ってきたと自負する人たちは、やっぱり人間とそれ以外の自然を分けて考えます。デカルトの「我思う、故に我あり」という有名な言葉がきっかけとされますが、自分とそれ以外の環境は違うものなのだと切り分ける。
人間が自分以外の対象を観察して、仮説を立て、いろんな実験をして仮説通りの結果になると「あ、自然はこういう法則で動いているのか」と客観的にわかります。それがずっと発展して今の西洋文明ができ上がり、分子生物学も宇宙ロケットも生まれました。
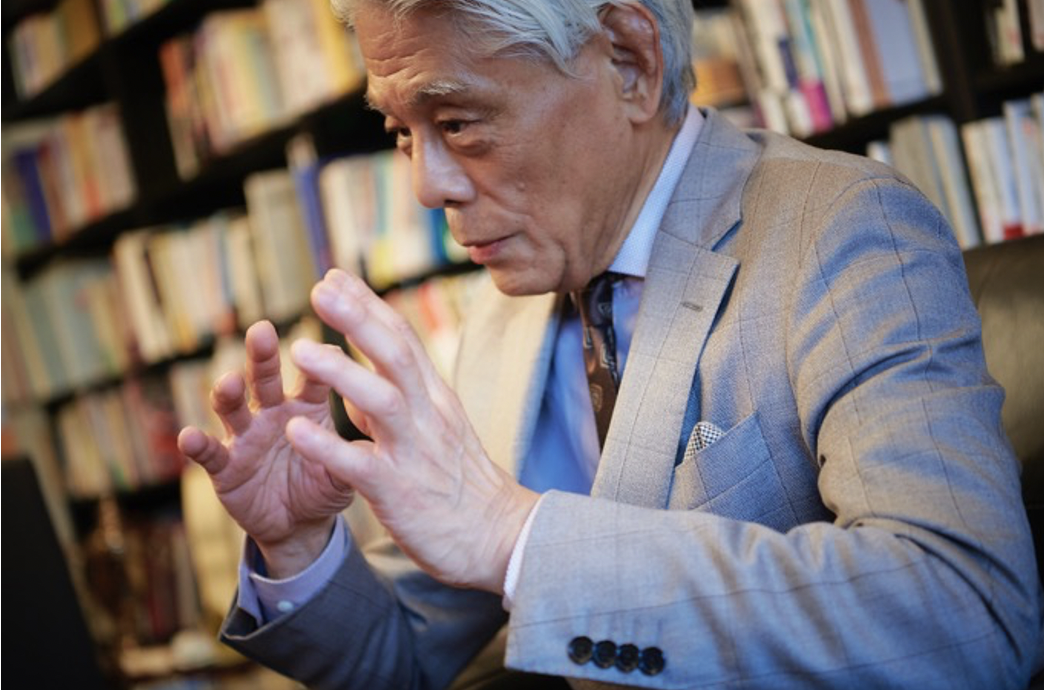
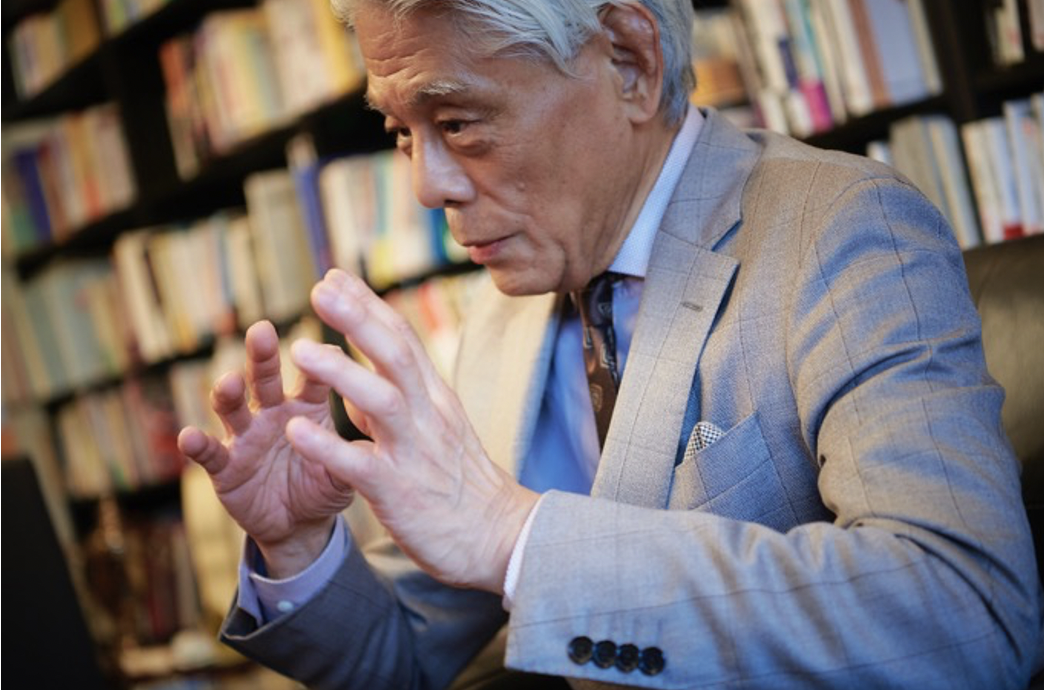
近藤先生
西洋的な発想、いわゆる「主」と「客」の二元論ですけども、それだけで割り切れないものが、本当はたくさんあります。先ほどから話題にしてきた目に見えないもの、これは二元論に慣れているとどう扱っていいかわかりません。人間は自然環境と切り離されていない、自然環境の一部でしかないという日本文化の考え方とは根本的に異なるものです。
ー
そもそも、どうして日本にそのような考え方が根づいたのですか?
近藤先生
私は気候風土が相当影響していると思います。日本列島は比較的温暖な気候で四季があって、春になれば花が咲き、秋になれば美味しいものがある。でも、ときにはすごい地震があったり、火山が噴火したり、台風が来たりする。自然に翻弄されつつも、自然によって生かされてきました。
結局、自分は自然の一部なのだ、ひどい目に遭ってもその後に報われるから、抵抗なんかしても意味がない。こうして自然を包括的に受け入れる考え方が日本では生まれたのではないでしょうか。それに対して、二元論で割り切る手法が科学技術の力をつけてしまい、自然の制約を表面的に乗り越えてきたのが西洋です。両者の文化が異なるのは、こうした面からも言えるのでしょう。
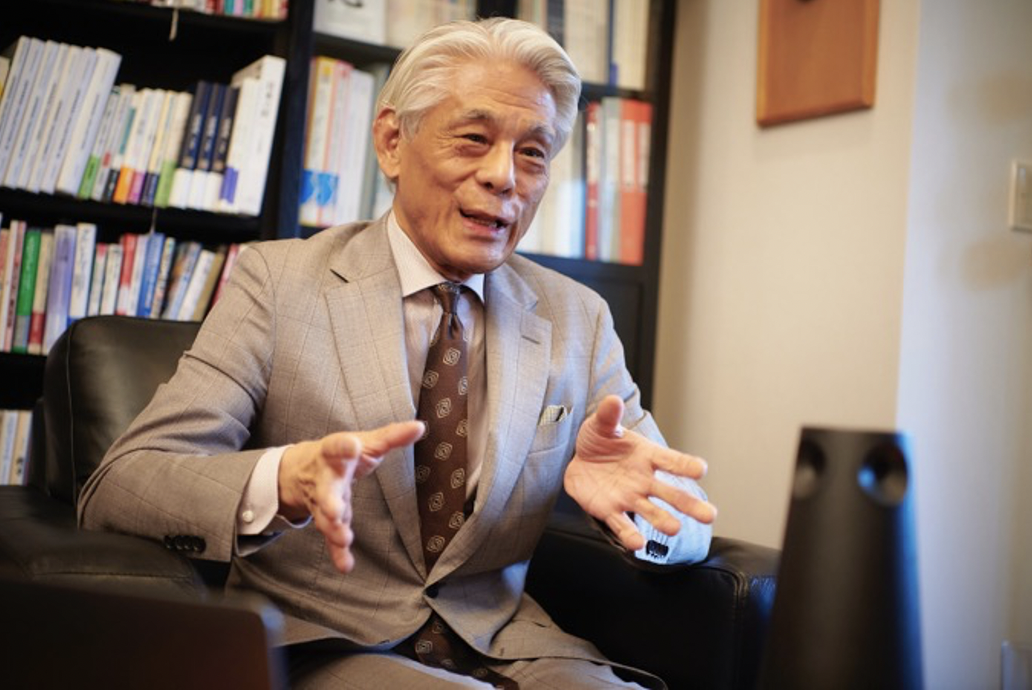
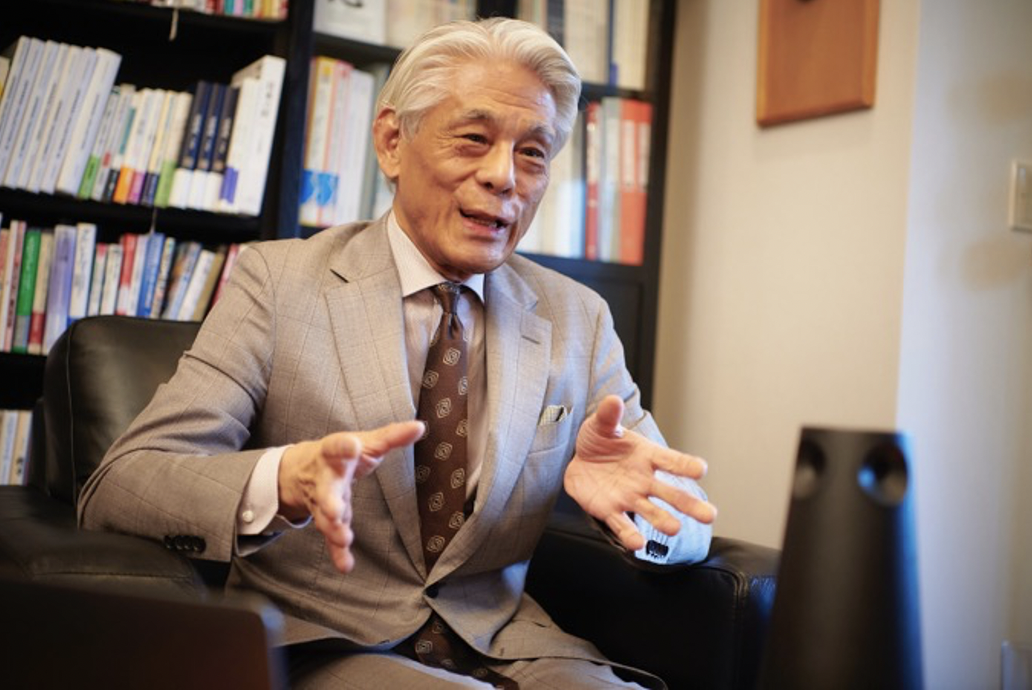
京都の曼殊院というお寺には、微生物を供養する「菌塚」があります。これはお酒や醤油、味噌づくりに使った菌たちを弔うためのものなんです。天野エンザイムの研究者さんたちも、日常的に数億、数兆の菌を犠牲にして研究をしているから、こうした塚を建てる考えにとても共感すると言っていました。
でも、菌塚へ海外のお客さんをお連れすると、欧米の方たちだとあまりピンと来ないことが多いみたいですよ。中国やアジア圏から来る方たちは、なんとなく日本の人と理解が近いようですね。



近藤先生
人間の本来の姿は自然の一部であり、周りの環境と連動して活動しています。だから命のもとを自然からいただくし、酵素の働きにも助けてもらう。そして細胞が古くなったら、どんどん外へ出して自然の循環に乗せる。こうした流れが生物学でわかってきたけれど、昔はそんなことはわかりません。でも、日本では客観的に分析して実験して、という自然科学のプロセスを経なくても、ずっとそういうものだとされていた。自然の移り変わりの中で、民族の存亡の危機を経験することなく比較的おだやかに生きてきたから、そこまで感じ取れたのかもしれません。
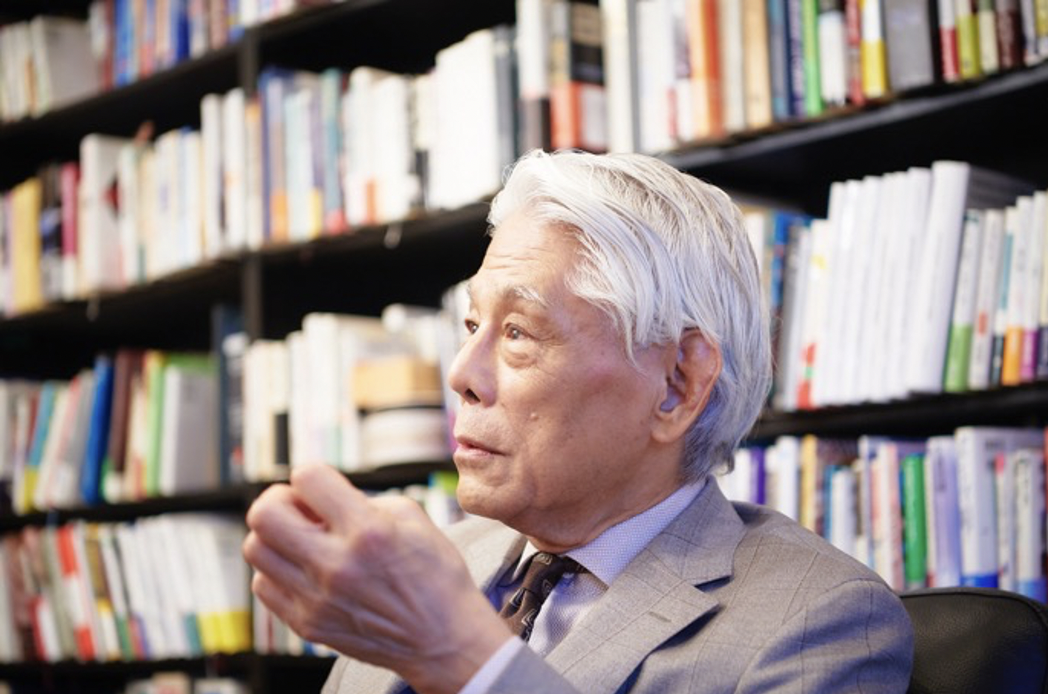
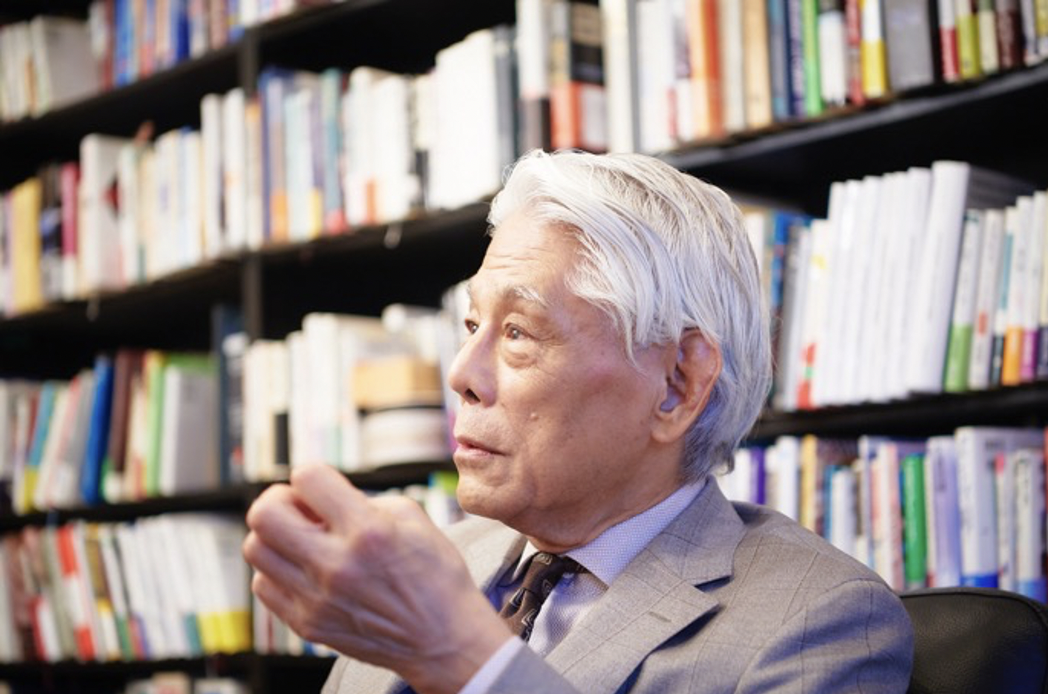
近藤先生
近代科学を誕生させた西洋合理主義の手法は、人間の目には見えないこと、あるいは頭では考えられないことを捨てて分かることのみに注目し、そこにある法則を利用して生活を便利で楽にするという意味で非常に有意義なものです。しかし、それが行き過ぎると自然を破壊してしまう。自然は単なる材料であり、人間にとっての資源である、という極端な方向に傾きがちです。
日本の文化には「人間も自然の一部である」という考えがあり、自然における摂理を守ってきました。こうした文化を踏まえたうえで西洋合理主義的な科学の手法を使うと、これからの社会はバランスの良い発展ができるのだと思います。
西洋と東洋、なんとなく理解していた文化の違いについて、自然との関係でわかりやすく明かしてくれた近藤さん。世の中には目に見えないもの、割り切れないものがたくさんあるから、謙虚さを持つことが大切という言葉が印象的でした。後編では、日本文化の「移ろい」というキーワードに注目。これから世界に伝えたい自然観、さらに日本の研究者に期待される役割について伺います。
<後編>へ続くこの世界のあらゆる場面で活動する酵素、その新たな可能性を求めて。
現在、さまざまな分野で活躍中の人々のもとを「酵素くん」と一緒に訪ね、お話をうかがうコーナーです。